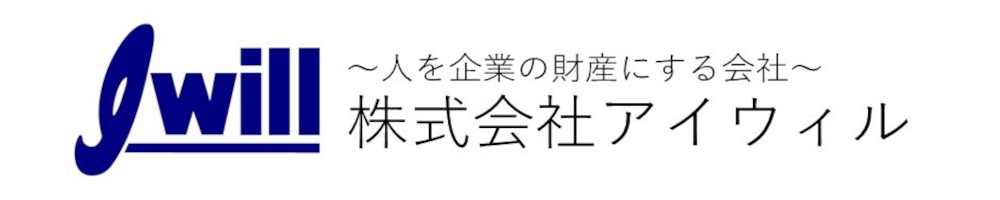染谷昌克の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 433」 染谷昌克
歩き続ければ必ず越える
バブル時代は、企業が社員教育に力を入れることはステイタスだった。バブルが弾け教育の歩みを止めた企業は多い。それらの企業は、衰退または淘汰された。リーマンショック時、それを学んだ経営者は緩めども歩き続け、平成を勝ち抜いた。今、コロナが収まり経済コロナ禍に突入している。
継続なくして社員の評判は保てず
研修施設の管理人が利用者の激減をこぼしていた。五年前(コロナ以前)に比べて利用者が半分以下に減っている。
いわれてみれば、二百人収容の食堂でアイウィルの十五人だけがぽつんと食事をしている日がよくある。
この現象は二つのことを語っている。
一つは、企業がいかに無駄な研修をやっていたかということ。景気が悪くなったらパタッと研修をやめてしまった。教育をしているという事実だけの時間つぶしで効果のない研修だった。経費節減のために真っ先にやめたのである。
もしくは、手軽なリモート研修に切り替えた。カメラを通してのリモート研修は、学ぶ側の意識が高くないと効果は薄い。講師の力量も大きく関わってくる。並みの講師が学ぶ意欲のない生徒に行う研修やセミナーは、実施したという事実しか残らない。
二つ目は、こんなに景気が悪くても、社員教育に真剣な企業が依然として存在しているということ。
アイウィルのお客様も順風満帆の企業ばかりではない。仕事が減っている。売り上げが落ちているが、トップは教育を続けている。
ある社長は「お金のあるうちに」といい、ある社長は経費節減で他のことを絞りながら、研修派遣を続けている。この姿勢には本当に頭が下がる。
コロナ禍の期間中にこんなことがあった。
毎年三十名以上の新卒が入社する会社。アイウィルの新入社員研修を採用している。
コロナ禍が始まった二〇二〇年の春、緊急事態宣言のため研修を延期。四月予定だったものが、五月になり六月七月にと延びていった。
八月に「九月には全国の営業所に配属になる。時間や経費を考えると今年は社内でやる。アイウィルはキャンセルします」と連絡が入った。
大きな商いを失ってしまった。十月に入り人事担当者から電話が入った「アイウィルさん、何でもいいから研修やってくれ」と。
聞けば現場に配属された新入社員の評判が悪い。挨拶はできない、返事の声が小さい、表情が暗い、メモは取らない、相手の目を見ないで話を聞く、コミュニュケーションは取れない。
今年の採用はいったいどうなっているのかと、現場から人事部にクレームが入った。例年との違いは、アイウィルの研修を受けなかったことだけ。
会社全体に危機感はあるか
社内を見渡してみると、危機感のない社員がまだ多い。
会社の危機。社長は青色吐息。社員も五年前のようにのんびりしてはいない。緊張し真剣に仕事をしている。
といいたいが、社員の中にはまだ環境の変化に合わせて自分を変えることができていない人が少なくない。
自分の能力を伸ばす努力をしない。仕事の工夫改善をしない。いわれなければ自分の欠点を直そうとしない。辛いとすぐ音をあげて逃げ出す。楽なほうへ楽なほうへ行きたがる。何でも人に頼る。上司に叱られるなど些細なことを根に持ってやる気をなくす。幅広く学ぼうとしない。
環境がこれだけ厳しくなっているのに、まだコロナ前と同じ気分でいる。そのため会社からきつい仕事を命じられたり、重いノルマを課せられたり、昇給や賞与の額が少なかったりすると、ふくれて暗くなる。会社を辞めたくなる。
こんな社員がまだ多い。若い社員だけでなく「長」の肩書をもらっている中堅ベテラン層にもこんな人がいるから問題は深刻である。
あるメーカー。仕事が減って機械が遊んでいる。危機感を持ったトップはこんな時期だがと、課長を研修に参加させた。課長は当初こそ頑張ったが、二ヵ月目に息切れして、通信教育のレポートを提出できなくなった。
社長が専務に「課長はなぜこの程度の勉強ができないのか。私が直接注意しよう」といった。
専務は「仕事はちゃんとやっている。夜遅くまで頑張っている。社長が直接いうのは最後通牒(つうちょう)になる。荒っぽすぎる。周囲にも悪い影響を与える」と反対した。
部長が課長に「きちんとやるように」忠告した。
課長は研修を続けなかった。月日が経った。
社長は「私が最後通告する」といった。専務も部長もほかの幹部も「それはいけない」と反対した。課長は必要な人である。課長がいなくなれば困る。研修を途中でやめたことは不問に付すべきだという。
社長は孤立した。そしてまた月日が経った。
五年前と同じ考え方では滅びる
課長は「今更こんな勉強をしたって無駄だ。この勉強をする時間を仕事に回すほうがずっと意義がある」といった。そして毎日、夜八時、九時まで仕事をした。
これは課長の〝心の合理化〟である。勉強が辛いから仕事に逃げた。一人前の管理者になるチャンスを自ら放棄した。会社の期待を裏切った。
社長のいうとおり、この程度の勉強がきちんとできないようではこれからの厳しい環境を乗り切れない。
それにしても、社長の正論を潰してしまった専務以下の幹部は何を考えているのか。
自分の会社がどんな状況にあるのかわかっているのか。
この会社は社長以外の社員が、会社の将来を真剣に考えていない。このままいけば、五十年の伝統も何の役にも立たずに衰亡するという〝事実〟がわかっていない。
社員は会社が危機だとは感じているが、今まで身につけてきたやり方考え方を変えることができていない。五年前と同じ考え方で問題を処理しようとしている。
日本は変わった。環境は変わった。会社の進むべき方向も変わったのだ。五年前と同じ考え方では滅びる。
会社に所属する人は、今までの考え方を一八〇度方向転換する時期にきている。今社員にもっとも必要なのはこの『自覚』である。
現状を認識し、課題をあぶり出す。ここから生まれる「気づきと反省」から変化の必要性を理解した時、社員の行動が変わっていく。