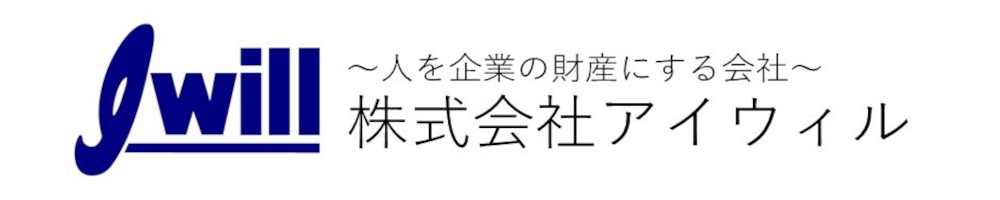染谷昌克の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 434」 染谷昌克
管理者としての上級任務
ナンバー2養成研修も四年目を迎えた。トップである社長の補佐役育成研修として教育効果は高い。修了生は現場で獅子奮迅の活躍をしている。研修の回数を重ねるうちに、補佐力は管理職全員、また一般社員、誰においても必要な能力であることを確信した。
管理者が果たすべき任務
管理者になったが、役職に見合う行動がわからないという人。プレイングマネージャーが多い日本の中小企業には割と多い。目に見える業績向上や部下育成は当然大事なことだが、こんなこともある。
ある男を部門長にした。業績を上げ、部下をきちんと育てることができる。幹部になることを期待した。半年経って、業績も順調。部門の管理もしっかりできている。ただ、社長から見るとしっくりこない。期待外れとまではいわないが、想定内の活躍である。
優秀だからこそ会社の中枢を担う存在になって欲しかったが、そこまでではなかった。
管理者の任務は
一、業績を上げる
二、部下を育てる
三、トップ(上司)の補佐をする
この三つはどれも大事。高いレベルで三つのバランスが取れているのが優れた管理者である。
売り上げは上げるけれど、下についた部下が全く育たない。部下が辞めてしまう。部門はまとまっているが、実績が出ない。会社の方針とは違うことをする。これでは困る。
このケースはよくある。その大半はトップ補佐のできない管理者である。社長に近くなるにつれ、重要になってくるのが「トップ補佐」である。
組織の中間に位置する人、管理者は部門の業績と部下育成に責任を持たなければならない。
もうひとつ忘れがちな任務がある。上司の補佐という任務である。これを「どうでもよい小さな任務」だと思っている人は、この任務の意義がわかっていない人であり、優れた管理者とはいえない。
一般社員にも上司補佐という任務はあるが、一般社員は与えられたノルマの達成、命じられた仕事をきちんとすることが、そのまま補佐になる。
管理者であればそうはいかない。この任務を強く自覚し、行動に表すことを求められる。
よく〝上ばかり見ている管理者〟がいる。上にゴマをすり、なんでも鵜呑みにして部下に伝える。上のご機嫌をとることに汲々としている。
この人は上司をよく補佐していることになるか。上司の顔色を窺い、機嫌をとることは〝補佐〟という任務にはほとんど関係ない。これは補佐ではなく保身。自分可愛さに権力に媚び、部下を腐らせる組織の有害分子である。
大統領補佐官、社長室室長、秘書といった人は補佐そのものを仕事にしている。それに比べ専務、常務、部長、課長といった管理者は補佐が仕事の中心ではない。しかし、部下を育てることも部門の業績をあげることも、広い意味では補佐になる。なので上司補佐を全くしていない人はいない。
補佐という任務を自覚して、その任務をきっちり果たす人は、己の立場を理解している人である。信頼に値する人。そこがあいまいな人は信頼できない人であるとも言える。
明確な立場を学べる教材務
司馬遼太郎は著書『燃えよ剣』のなかで、新選組の土方歳三を優れた管理者として描き出している。
それによれば、烏合の衆であった新選組に、あれだけの仕事ができたのは、副長土方歳三の力量によるところが大きい。
ある時、沖田総司が土方に話しかける。
「土方さんは憎まれていますよ。蛇蝎(だかつ)のように」
「近藤隊長は憎まれていまい」
「そりゃ近藤さんは慕われています。土方さんと違って」
「それでいいんだ。俺は蛇蝎だ」
「……」
「結党以来、いやな命令、厳しい処罰の決定はすべて俺の口から出ている。近藤の口から出させたことは一度もない。だから俺は蛇蝎のように憎まれる。しかし、その蛇蝎の上に神様のような親分がいるというのが隊士の救いになるんだ。
いいか、総司。俺は副長だ。副長が隊士の人気取りを始めたらどうなる。苦い命令が近藤の口から直接出る。すると近藤が憎まれる。隊士の不信や不満が募る。こうなると抑えが効かない。ちょっとしたことで爆発して、隊はバラバラになる。
そうならないために副長がすべての憎しみを被るんだよ」
この土方歳三の言葉に、中間管理者の立場意識が端的に表現されている。
管理者は下にべったりくっついてはいけない。もちろん上ばかりを見ているのもいけない。上の視線を背中に感じながら、部下の目を外に向けて、部下とともに外を見る。こういう立場にある。
この立場にある人は、上司の考えをよく理解していなければならないが、上司と全く同じ考え方をしても、それだけでは任務を果たせない。上司と同じ立場にあるのではなく、上司を補佐する立場にあるからである。
組織に必要な本物の人務
補佐は上に気に入られるためにするものではない。上に引き立ててもらおうとするものでもない。出世の条件ではない。
〝補佐〟は組織が必要とするものである。組織が健全に機能するには、管理者の補佐任務遂行は必須。たとえ大将が暗愚であろうと、信頼するに足らざる人物だろうと。管理者は組織の維持と強化のために、上を補佐しなければならない。
反論もあるだろう。「こんな滅私奉公的な考えは納得できない」「若い管理者にこんなことを言っても通じない。昭和の考え方、と一蹴されてしまう」
誰しも自分が一番大事。それは、今も昔も同じである。自分より大将の方が大事なはずがない。上を守って自分を犠牲にする行為も、上のためではなく本当は自分のためである。
人はひとりでは弱い。だから組織に所属する。その組織が崩壊すれば自分が困る。そうならないため、自分に与えられた〝補佐という任務〟を果たすのである。
危機が訪れた時、上を補佐してその危機を乗り切るか、上を見捨てて逃げ出すか。どちらを選ぶかは本人の自由である。
しかしたいがいの場合、後者の道は前者の三倍苦しい。自分が依存する組織を維持するために上を助ける方がはるかに楽である。
時代が変わっても、組織が人の関わり合いで成り立つという〝組織の本質〟は変わらない。若い人ばかりの会社でも、管理者としては土方歳三が正しいのである。