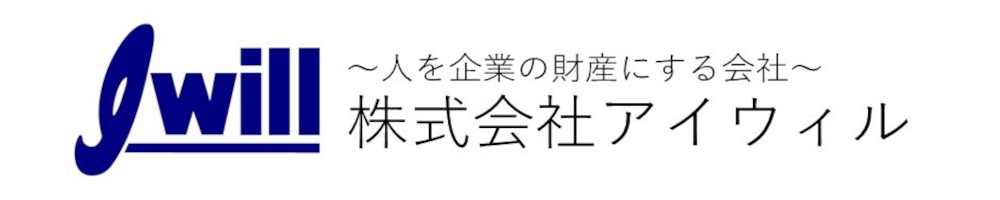染谷昌克の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 443」 染谷昌克
忘れることに価値はあるか
学校の勉強は「覚える」が主流。試験は覚えたことの確認作業。覚える能力の良し悪しで成績の帰趨(きすう)が決まる。もちろん大事な能力ではあるが、実社会では学生時ほど重要な能力ではないのでは。記憶力がよくて学校の成績がよかった人が必ずしも実社会のトップではないのだ。
「覚える」至上教育でいいのか
覚えることが苦手な人は学校の成績がよくない。小学校で漢字の書き取りができない。中学高校で社会、理科ができない。もちろん英語もできない。
この人は努力(時間をかけて勉強)してもいい点が取れないので〝自分は頭が悪い〟と思うようになる。これが潜在意識に染み込んで勉強意欲をなくす。必然的にいい高校、いい大学に入れない。社会人の大半はこうした人である。
大手企業に勤めるエリートや官僚、難しい国家資格に若くして合格する人たちなどは、覚えることが得意な人である。この人を日本ではエリートと呼んでいる(本当のエリートは記憶力が優れた人ではなく知識・教養・人格はもちろん、思考力に優れ本職に関係ないことにも広く精通している人である)
受験問題も、覚えていればできる問題が多い。
東京大学の学生に聞くと「中学高校は授業を聞いて、教科書を覚えればほぼ満点が取れる。難しいことではない。学校では〝覚える能力〟に一番の価値がある」という。
世の中ではこの能力はそれほどの価値はないらしい。
覚える能力が劣る人、つまり学校の成績があまりよくない人の中に多くの逸材がいる。
集団のリーダーシップをとる人、いい仕事をする人、画期的研究成果を上げる人、優れた芸術家・職人など少なくない。
最近では「地頭がいい」という表現をされる人も多い。思考力のある人。理解力や表現力を持ち、考える力のある人である。
「勉強嫌いです。学校の成績も酷いものでした」という社員がいる。いい仕事をする。優先順位や物事の取捨選択が上手い。問題の発見、改善ができる。任せて安心の社員である。
他人と違うのは〝メモ魔〟である。メモ帳、付箋、スマホを使い、情報整理だけでなく処理や管理まで行う。
記憶力がいいことの不幸
私は学校の成績はそんなに良くなかったが、覚えている能力は高かった。
いつどこで誰が何を、が自然と頭の中に浮かんだ。
「駅前の居酒屋で、部長と鈴木君と飲んでた時に部長はこう言いましたよ。あのとき蝶々柄のネクタイされてました」。
メンバーや状況まで覚えているので、相手も納得せざるを得なかった。
その場では、してやったり感があるが、時間が経つと後味が悪くいい気持ちではなかった。
家庭での小さないざこざで、妻に対してもこれをやる。必ず夫婦喧嘩になった。
覚えていることは優れていることだと思っていたが、実は不幸なことなのかもしれないと感じ始めた。
似たような話を聞いた。
ある社長は若い時から記憶力がいいことに自信を持っていた。「君は何月何日に、どこどこでこう言ったじゃないか」
「そうですか。覚えていないんですが、そう言いましたか」と部長。
すると社長には部長が誠意に欠けているように見えてくる。詰問の調子がきつくなる。部長はおたおたして、しなくていい弁解をする。
こうしたことが何回もあった。部長は、社長に呼ばれたり、社長からの電話があると動悸が起こるようになった。やがて病気になり退職した。部長のみならず幹部が何人も同じ道をたどった。
「こうやれといっただろう。覚えていないのか」これが社長の口癖であり、幹部は「いったいわない」の問答の後、納得いかないまま自分の非を認め謝るのが共通した態度だった。
社長は記憶力に対する自信があるゆえに、周りが馬鹿に見え信じられなくなった。そして人を何人も失った。
責めている中身は大事なことは少なかった。ただ〝忘れてしまっていること〟〝覚えていないこと〟が許せなくて幹部を強く責めるようになっていた。
記憶力がいいということは長所なのだろうが、このように短所にもなる。それも致命的な欠陥になりうるのだ。
幸い私は、十数年前から〝覚える力〟が激的に劣化してきた。勘違い、物忘れが増え「何だったっけ」を連発している。
家庭では妻に「あなたは物覚えがいいんでしょ。忘れたとは言わせないわよ」と詰められることもしばしば。「尻尾を巻いて逃げ回っている。
忘れる力も仕事能力のひとつ
覚える能力が劣るというのはいい換えれば「忘れる能力が優れている」ことである。忘れないことでよくないケースがある以上〝忘れる〟を能力といってもいいだろう。
忘れないことは不幸なことである。人生には楽しい思い出もあるが、辛いこと口惜しいことの方がたくさんある。それらがしっかり記憶され、絶えず心を支配するのは本人のためにならない。
二十年前にいわれた一言を昨日のことのように覚えていてその人を絶対に許さない。失敗した人のその失敗が今も鮮明にあるため、その人が成長しても認めない。一度嫌った人は一生嫌いぬく。人間関係が上手くいかない。
忘れないことは、一見優れた能力のように思えるが、過去の失敗や嫌な記憶までも抱え続ける。心の負担や行動制御が増え、前向きな行動や思考の妨げになることがあるのだ。
〝忘れること〟というと「だらしない」「覚えていないなんて恥ずかしい」といったマイナスの印象を持つが、忘れる力には重要な役割がある。
忘れることは、情報を整理し「今の自分に必要なこと」に意識を向けやすくすること。
私たちに求められる力は、「記憶力の良さ」だけではない。身の回りにある膨大な情報から、何を覚え何を忘れるかを考え、取捨選択する判断力である。
優れた人は、「すべてを覚えること」ではなく、「必要な情報だけを残し、過去にとらわれず判断を下すこと」ができる人。
忘れることは、怠慢でも逃避でもない。
私たちにとって、忘れる力を持つことは、冷静な判断、柔軟な思考、そして寛容な人材育成に不可欠なのだ。
忘れる能力を磨くには、メモを活用すればいい。メモに残したものを、定期的に必要な情報とそうでないものに仕分けする。繰り返していくうちに、不要な情報に縛られている自分の姿が見えてくる。
<経営管理講座バックナンバー>
- 2025/11 精神と行動を整える力
- 2025/10 経営者養成研修
- 2025/09 黒ひげ危機一発
- 2025/08 やさし過ぎるは、悪なり
- 2025/07 組織を統(す)べる力とは何か
- 2025/06 経験で育てるか、教え育てるか
- 2025/05 社長も、部長も、みんな若者だった
- 2025/04 人材は〝人財〟か〝人罪〟か
- 2025/03 管理者としての上級任務
- 2025/02 歩き続ければ必ず越える
- 2025/01 歴史を繰り返そう
- 2024/12 三十一年の歴史に幕
- 2024/11 増えてくる甘ちゃん族
- 2024/10 予期せぬバトンタッチ
- 2024/09 かつての〝学問〟に戻る時
- 2024/08 手書きが思考力の基礎
- 2024/07 高橋先生から学んだ事
- 2024/06 作文に特化した授業を
- 2024/05 精神強化と意識改革を
- 2024/04 積上げてきた美の遺産
- 2024/03 美に対する感性を磨く
- 2024/02 修復できない大被害が
- 2024/01
魁 としての奮闘の記録 - 2023/12 恥と秘密があってこそ
- 2023/11 外人と共生する社会か
- 2023/10 中国に魚は売りません
- 2023/09 捨てたものを見直す時
- 2023/08 経済で解決できない事
- 2023/07 悪運強し四七歳失業者
- 2023/06 有能でもNo2失格の男
- 2023/05 失敗が生んだ教育手法
- 2023/04 新会社を成功させたが
- 2023/03 私事よりも仕事を優先
- 2023/02 二十代は苦労勉強の時
- 2023/01 仕事と人間に恵まれて
- 2022/12 上司に頼られる社員に
- 2022/11 失敗と挫折は成長の糧
- 2022/10 たまには恥と失敗話を
- 2022/09 騒がせ屋の民主的小言
- 2022/08 昔通った道にまた来た
- 2022/07 自己啓発による勉強法
- 2022/06 甘えるな!甘やかすな
- 2022/05 勝利の方程式を作る人
- 2022/04 強く賢くやさしい人に
- 2022/03 しつけと指導の復権を
- 2022/02 歴史から何を学ぶのか
- 2022/01 歴史を学び新聞を読む
- 2021/12 大局観と先見性を磨く
- 2021/11 〝守り〟についての考え方
- 2021/10 居なければ探し育てる
- 2021/09 ナンバー2研修の意義
- 2021/08 会社に補佐役はいるか